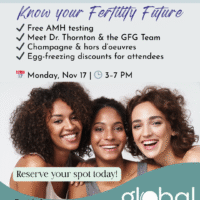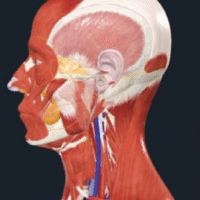〜あなたの未&#
在米日本人の健康と医療をサポートする「FLAT・ふらっと」がお届けする連載。アメリカで健康な生活を送るために役立つ情報を発信します。
毎年ワシントンDCの旧日本大使公邸で、がん医療に携わる日米の医療者や研究者が集うオンコロジーカンファレンスが開催されています。米国で 30 年以上にわたり血液腫瘍内科医として活躍し、このカンファレンスをけん引してきた武部直子医師に、その意義と経緯を伺いました。
がん治療と統括する血液腫瘍内科医
筆者はオンコロジーの専門家を志し、1990年代初めに米国に渡りました。オンコロジーはギリシャ語で「腫瘍が膨れる学問」、すなわち「がんの学問」です。アメリカでは血液腫瘍内科医をオンコロジストと呼び、循環器、呼吸器などと並ぶ内科学の大きな柱となっています。
日本では2018年にようやく腫瘍内科医が学会で認定され、まだ歴史は浅いのですが、米国では外科医や消化器内科医ではなく、血液腫瘍内科医ががん治療を統括しています。
30 年前、ニューヨークのメモリアル・スローン・ケタリングがんセンターでの研修では、「オンコロジー=臨床試験」という考えをまず叩き込まれました。再発して標準治療の効果が及ばなくなったときには、臨床試験中の新薬という選択肢があることを正しく患者さんに伝えることが、血液腫瘍内科医の責務です。
新たな治療は治療から
薬剤の承認には企業治験や医師が自ら計画する医師主導治験と呼ばれる臨床試験が必要です。米国では国立がん研究所(NCI)が国を挙げて医師主導治験を支援しています。一方、日本には当時、臨床試験を支援する国の仕組みがなく、腫瘍内科医も不足していたため、米国で承認された抗がん剤が日本では未承認で使用できない、いわゆるドラッグラグ(日米の薬承認格差)が長く続きました。
筆者がNCIでがん治療評価部門の上級主任研究員を務めていた2007年頃、グローバルオンコロジーを統括していた同僚から「日本の医師主導治験を支援し、日米共同試験を活発化したい」と協力を求められました。そこで、厚生労働省や衆議院議員の勉強会、内閣府、米国大使館をはじめ各国大使館主催のシンポジウムで講演するため何度も日本へ出張しましたが、費用や時間の負担が課題でした。
日米交流で日本の臨床試験を後押し
そこで発想を転換し、NCIに近いワシントンDCで、在米の日本人医療関係者や政府関係者を対象に、日本大使館主催のカンファレンスを企画しました。目的は、米国で得た知見を帰国後に日本で生かし、臨床試験のインフラ整備を政府に働きかけてもらうことでした。
日本大使館経済班の一等書記官の支援をいただき、NCIの研究者スタッフと協力して、2009年、ついに旧日本大使公邸で第1回日米オンコロジーカンファレンスを開催することができました。
 日米オンコロジーカンファレンス。国際的に活躍する日米の医師や研究者が登壇し、プレゼンテーションやディスカッションなどを行う
日米オンコロジーカンファレンス。国際的に活躍する日米の医師や研究者が登壇し、プレゼンテーションやディスカッションなどを行う
医療でもAIが大きなテーマに
その後、このカンファレンスは日本大使館と日本医療研究開発機構(AMED)との共催で続き、今年で 12 回目を迎えました。9月には「未来を形作る:AIでがん研究を飛躍させる」をテーマに開催。基調講演では、ジョンズ・ホプキンズ大学の教授が、人種や地域による格差を踏まえたがんの早期発見と予防について講演しました。また、AIを使った解析により、治療効果の予測精度が上がり、予後改善につながる事例も紹介されました。AIは膨大な臨床・遺伝子・画像データを解析でき、個々の患者に最適な治療法を探るうえで欠かせないツールになりつつあります。
日米の専門家が異なる視点を持ち寄ることで、新たな発想が生まれます。このカンファレンスを通じて、AIは人間の医師や科学者を置き換えるものではなく、その能力を高める存在であることを再確認しました。AIが患者さんに希望をもたらす可能性を信じ、今後も医療現場や研究に積極的に取り入れていくべきだと感じています。

武部直子
血液腫瘍内科専門医
弘前大学医学部卒。1991年に渡米。メモリアルスローンケタリングで血液腫瘍内科フェロー、メリーランド大学医学部助教授、米国国立がん研究所で臨床治験の責任者などを歴任後、現在はオクラホマ大学医学部内科教授、同大学スティーブンソンがんセンター臨床研究副所長。
●サポートミーティング情報●
乳がん、婦人科がん、その他のがん、転移がん、自己免疫疾患患者さんのためのサポートミーティング、シニアカフェなどをオンラインで定期開催中。参加費は無料。
スケジュールや詳細は、FLATのウェブサイトをご参照ください。この他にも、一般の方にもご参加いただけるウェビナーなども実施しています。
「FL AT・ふらっと」は、がん患者や慢性疾患、高齢者、特別支援が必要な子どもを持つ保護者、介護者など、在米日本人の健康を、広い範囲でサポートする団体です。
Website: www.flatjp.org
Email: contact@flatjp.org